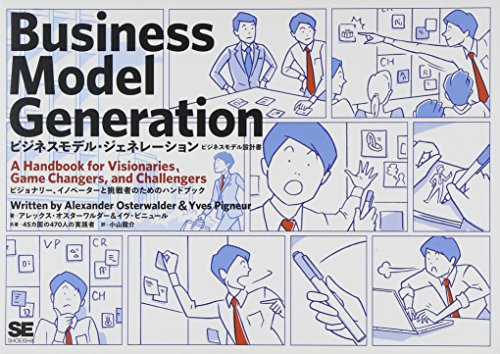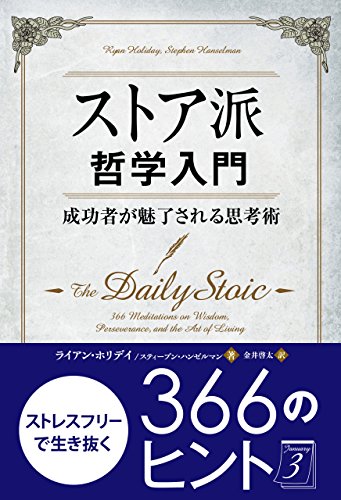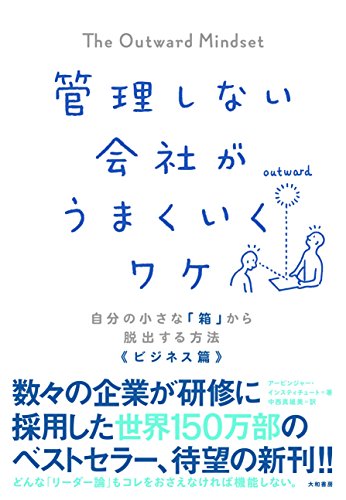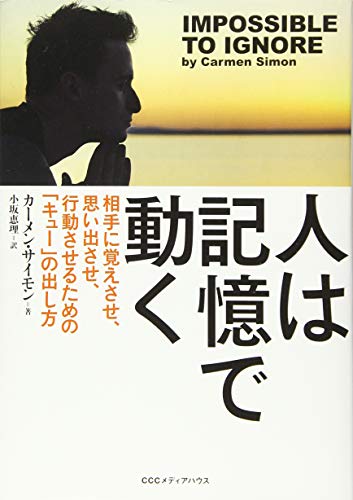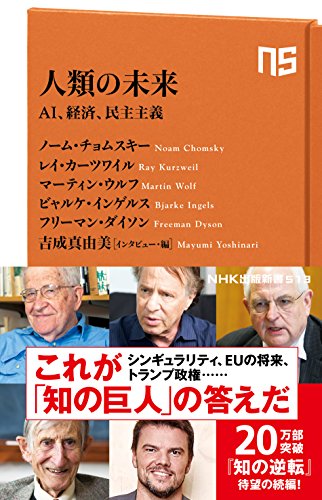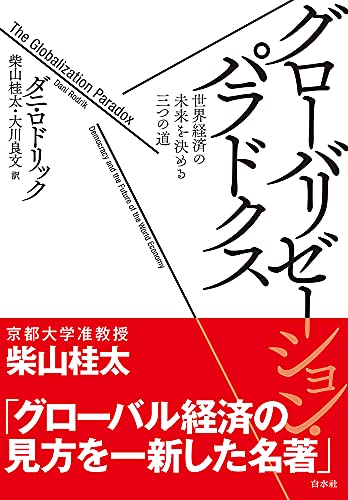まえがき
『このコンセプトは、4つの領域(顧客、価値提案、インフラ、資金)をカバーする、9つの構築ブロックで構成されています。』
リスト
- 【顧客セグメント(CS)】 誰のために価値を創造するのか?/最も重要な顧客は誰なのか?
- 【価値提案(VP)】 顧客にどんな価値を提供するのか?/どういった問題の解決を手助けするのか?/顧客のどういったニーズを満たすのか?/顧客セグメントに対してどんな製品とサービスを提供するのか?
- 【チャネル(CH)】 どのチャネルを通じて、顧客セグメントにリーチしたいか?/今はどのようにリーチしているのか?/チャネルをどのように統合できるのか?/どのチャネルがうまくいっており、どのチャネルが最も費用対効果が高いか?/チャネルを顧客の日常と、どのように統合すればよいのか?
- 【顧客との関係(CR)】 願客セグメントがどんな関係を構築、維持してほしいと期待しているのか?/どんな関係をすでに構築したのか?どれくらいのコストがかかるのか?/ビジネスモデルの他の要素とどう統合されるのか?
- 【収益の流れ(R$)】 顧客はどんな価値にお金を払おうとするのか?/現在は何にお金を払っているのか?どのようにお金を払ってるのか?/どのように支払いたいと思っているのか。全体の収益に対して、それぞれの収益の流れがどれくらい貢献しているのか?
- 【リソース(KR)】 価値を提案するのに必要なリソースは何だろうか?/流通チャネルや顧客との関係、収益の流れに対してはどうだろうか?
- 【主要活動(KA)】 価値を提案するのに必要な主要活動は何なのか?/流通チャネルは?顧客との関係は?収益の流れは?
- 【パートナー(KP)】 主要なパートナーは誰だろうか?主要なサプライヤーは?/どのリソースをパートナーから得ているのか?/どの主要活動をパートナーが行なっているか?
- 【コスト構造(C$)】 ビジネスモデルにおいて特有の最も重要なコストは何だろうか?/どのリソースが最も高価だろうか?/どの主要活動が最も高価だろうか?
あとがき
まえがきを含めて、『ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書』より。リストは本文を少しだけ編集して引用しました。
9ブロックの位置関係が重要なので、“ビジネスモデル・ジェネレーション”で画像検索すると感じが掴めます。
項目数は多いですが、流れがはっきりしているので、図を描きながら理解すれば頭に入ります。チェックリスト代わりに使うべく収集。
- タイトル: ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書
- 著者: アレックス・オスターワルダー(著)、イヴ・ピニュール(著)、小山 龍介(翻訳)
- 出版社: 翔泳社
- 出版日: 2012-02-10