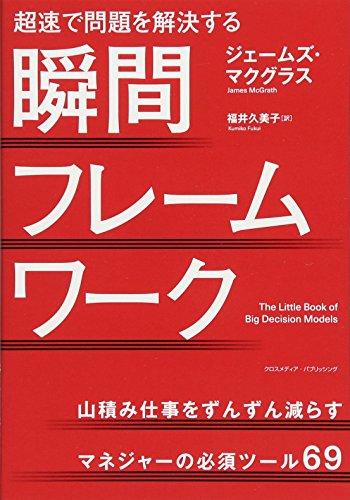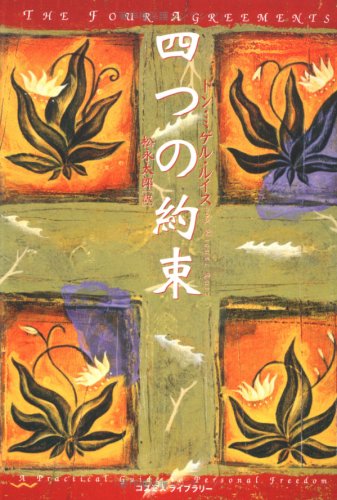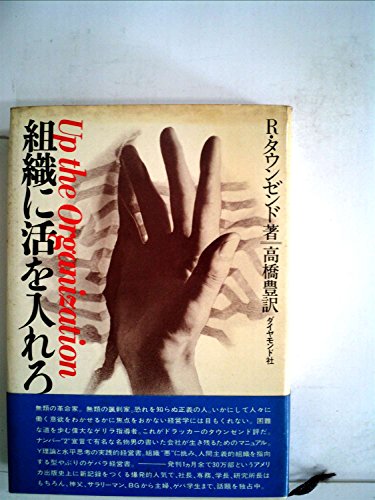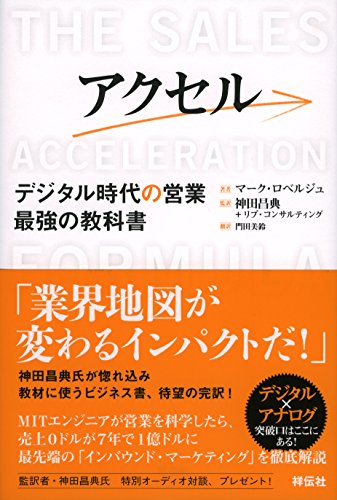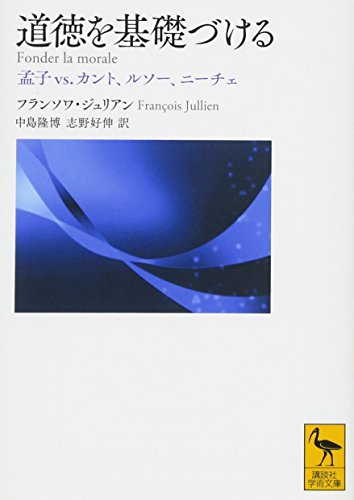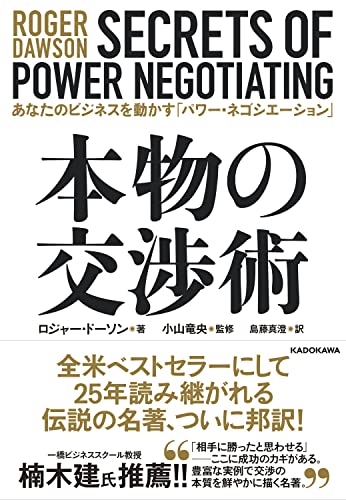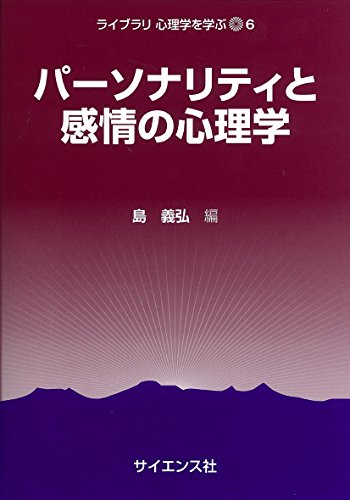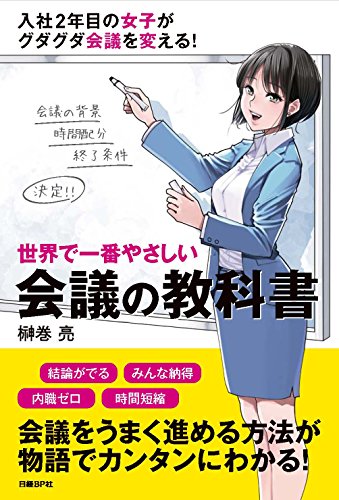まえがき
『四つの約束』の著者、ドン・ミゲル・ルイス博士は、自分の価値観に従って誠実に生きる方法を、シンプルに提案しました。
リスト
- 正しい言葉を使うこと …… 本音で語り、語ったとおりに行動する
- 何事も個人的に受け取らないこと …… 他人が何を言ったとか、何をやったと心配するのはやめる
- 思い込みをしないこと …… 誰とでもはっきりした言葉でコミュニケーションを取る
- 常にベストを尽くすこと …… 自分のコンディションにかかわらず、毎日、その日にできるベストを尽くす
あとがき
まえがきを含めて、ジェームズ・マクグラス『瞬間フレームワーク』(クロスメディア・パブリッシング、2017年)より。
できれば『四つの約束』を読んでリストを更新したいと思います。
- タイトル: 瞬間フレームワーク
- 著者: ジェームズ・マクグラス(著)、福井 久美子(翻訳)
- 出版社: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 出版日: 2017-02-20
この本からの他のリスト
- タイトル: 四つの約束
- 著者: ドン・ミゲル ルイス(著)、Ruiz,Don Miguel(原著)、太郎, 松永(翻訳)
- 出版社: コスモスライブラリー
- 出版日: 1999-04-01