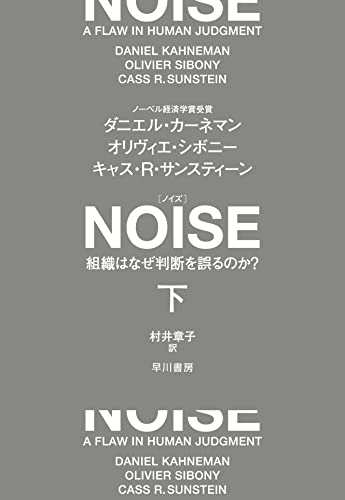まえがき
『衛生管理を意味するハイジーンという言葉を選んだのは、ノイズを減らすのは衛生管理と同じく、特定できない敵に対する防御だからである。』
リスト
- 判断の目標は正確性であって、自己表現ではない
- 統計的視点を取り入れ、統計的に考えるようにする
- 判断を構造化し、独立したタスクに分解する
- 早い段階で直感を働かせない
- 複数の判断者による独立した判断を統合する
- 相対的な判断を行い、相対的な尺度を使う
あとがき
まえがきを含めて、ダニエル・カーネマン、オリヴィエ・シボニー、キャス・R・サンスティーン『NOISE 下: 組織はなぜ判断を誤るのか?』 (早川書房、2021年)より。リストは本文見出しを引用して作成しました。
個人的には4が印象に残りました。
情報や証拠の注意深い検証を行ったうえでの直感的な判断であれば、パッと思いついた直感的な判断に数倍まさる。だから直感を全面禁止するにはおよばないが、できるだけ遅らせ、十分な情報を得たうえで規律をもって働かせるべきである。
タイトル: NOISE 下: 組織はなぜ判断を誤るのか?
著者: ダニエル・カーネマン(著)、オリヴィエ・シボニー(著)、キャス・R・サンスティーン(著)、 (編集)、 (イラスト)、村井 章子(翻訳)
出版社: 早川書房
出版日: 2021-12-02