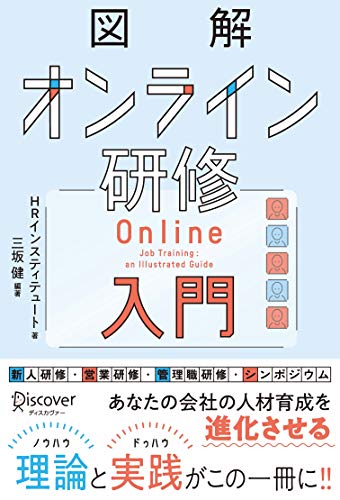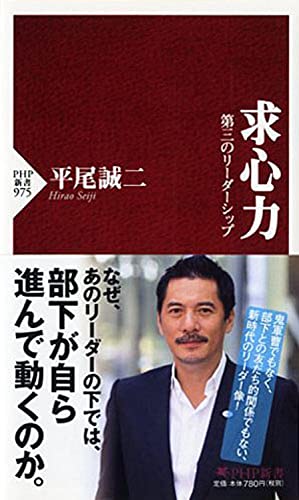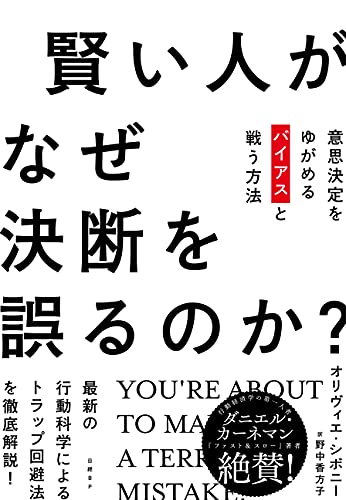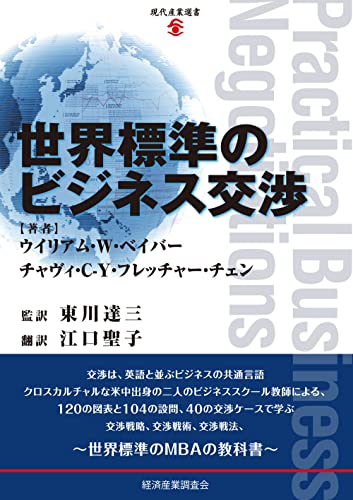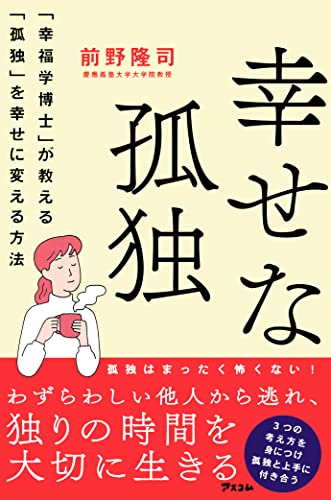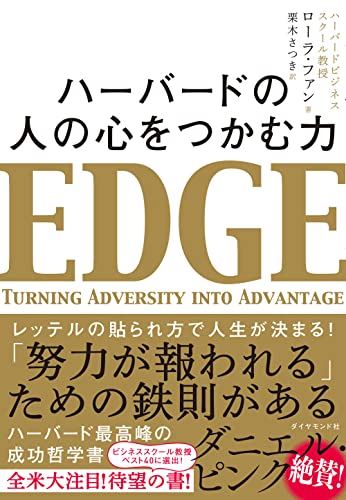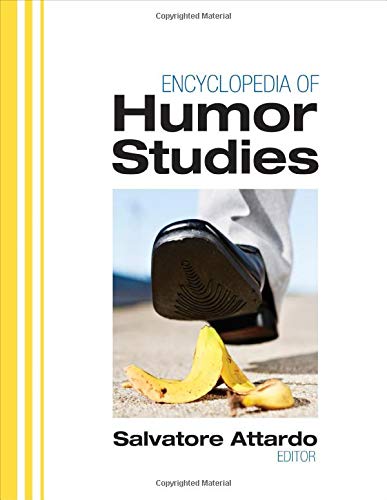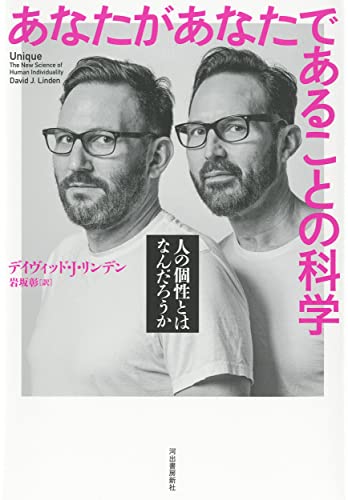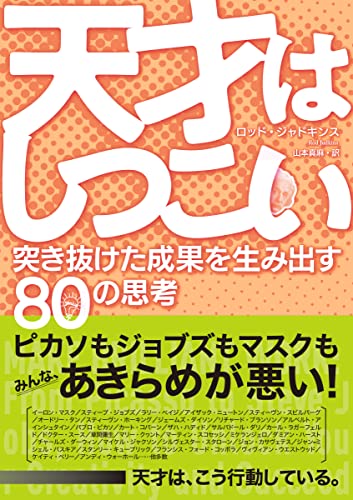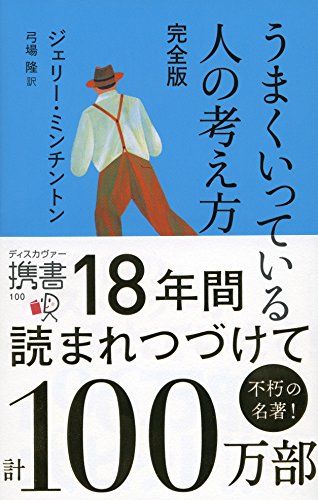まえがき
『会議を改善するシンプルなやり方は、この4つを整えて可視化することだ。』
リスト
- Outcomes(成果): 会議の終了時点で何が起きていてほしいか。書いて可視化しておくとよい。
- Agendas(アジェンダ): 話し合われるべき項目のリスト。それぞれに費やす時間の見積もりも。
- Roles(役割): 果たすべき役割を明確にしておく。メタファーを用いるとよい。例えば運転手、コーチ、レフェリー、デザイナーなど。
- Rules(ルール): 予見される問題にどう対処すべきかを合意しておく。どうやって合意を形成するか。一人の話が長くなったらどうするか。PCやスマートフォンを使ってよいか。
あとがき
まえがきを含めて、”4 Steps To Transform Your Meetings” (fastcompany.com) より。まえがきもリストも本文からの要約・引用です。
OARRという単語はHRインスティテュート、三坂 健『図解 オンライン研修入門』 (ディスカヴァー・トゥエンティワン、2020年)で見かけたと思いますが、手元のメモには本のタイトルとOARRという単語しか残っていなかったので、先述の記事から起こしました。重要な順でいえば OARR ですが、覚えやすさでいえば ROAR がよかったかな。
Roles(役割)は、「あなたは会議の運転手役」と固定的に割り当てるのではなく、いくつかの役割を意識して使い分けようというニュアンスだと理解しています。
- タイトル: 図解 オンライン研修入門
- 著者: HRインスティテュート(著)、三坂 健(著)、三坂 健(編集)
- 出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 出版日: 2020-10-23