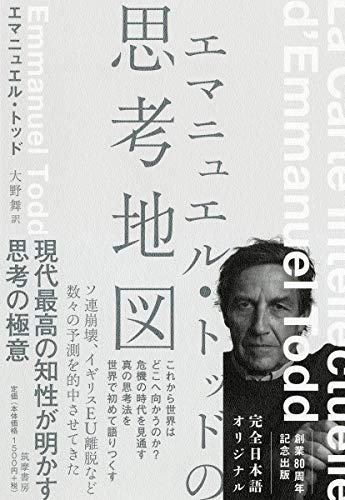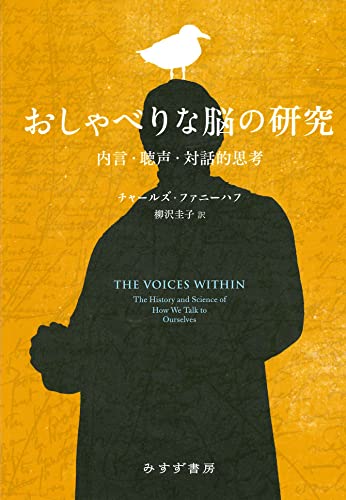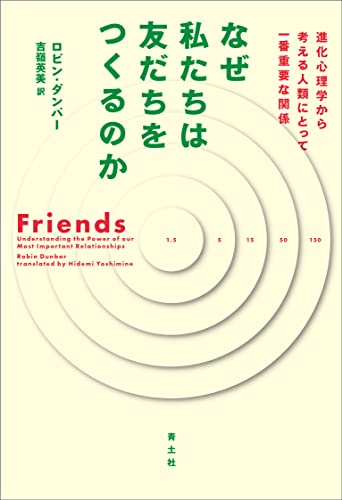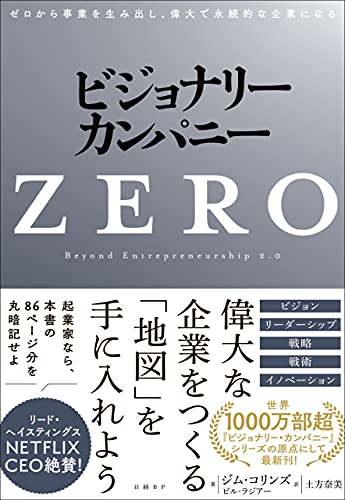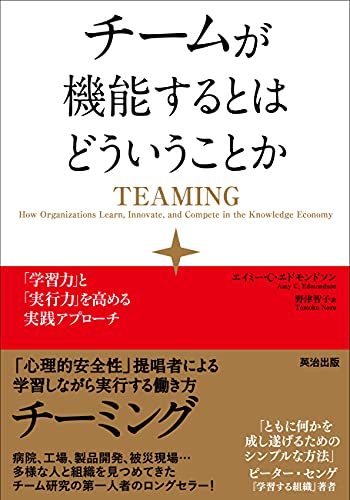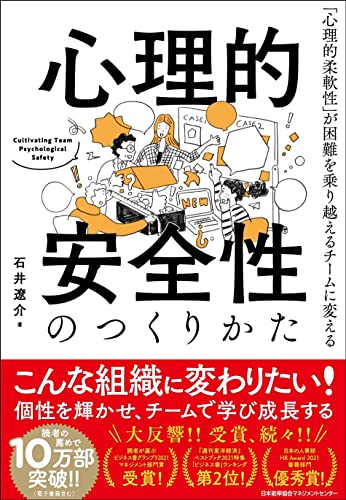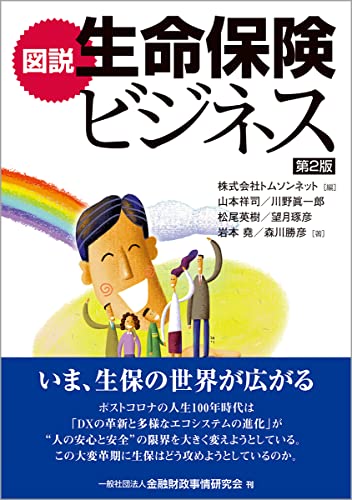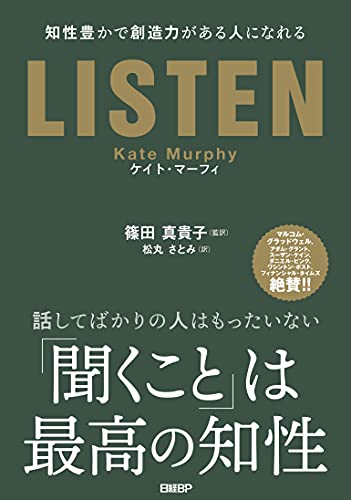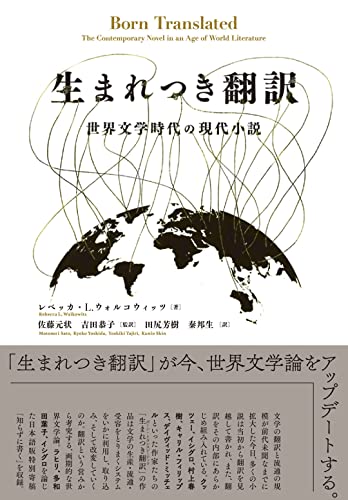まえがき
『私の思考の方法というのは、どこかしら芸術家のような部分があるのだと思います。(略)予測という行為には、これまで私が得てきた知識、研究、アイディア、理論、価値観、そうしたすべてが含まれているのです。』
リスト
- 経験主義 …… 現実への服従。物事が描写できる程度のしっかりとしたデータが集まるまで待つ。
- 対比 …… 経験主義的フェーズで得られたデータと自分自身の経験や歴史とを対比させる。
- 芸術 …… 本能、直感、歴史家としての経験を自由に解放させ、いくつかの予測を断行する。
あとがき
まえがきを含めて、エマニュエル・トッド『エマニュエル・トッドの思考地図 』 (筑摩書房、2020年)より。リストは本文及び図表からの編集・引用です。
「現実への服従」という印象的な言葉については引用部分の少し前に記述があります。予断を持たずにデータが集まるのを待つという意味合いです。
ビジネスでは仮説思考が人気ですが、未来予測の方法論はわりにこのような感じで、まず虚心にデータに浸ってから洞察の訪れを待つようなプロセスが多いように思います。
まえがきに含めましたが、著者は未来予測をするときの自分を画家のような芸術家になぞらえています。
イメージしてもらいたいのは筆を握った一人の画家です。キャンバスを前に、これから未来に訪れるものを描こうとしている画家がそこに見えてくるのです。
- タイトル: エマニュエル・トッドの思考地図
- 著者: エマニュエル・トッド(著)、大野 舞(翻訳)
- 出版社: 筑摩書房
- 出版日: 2020-12-23