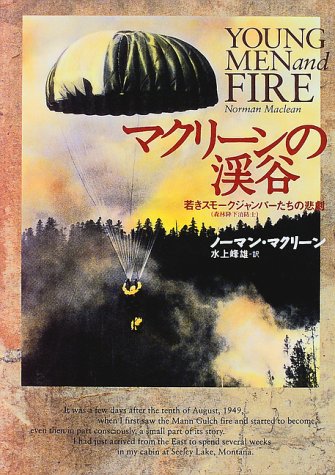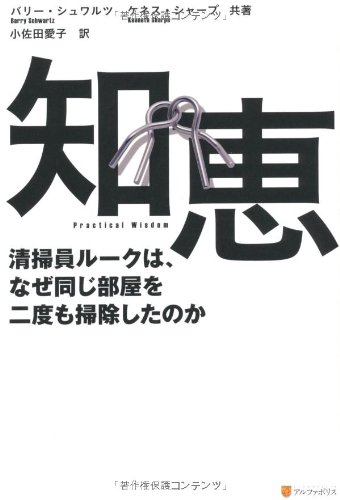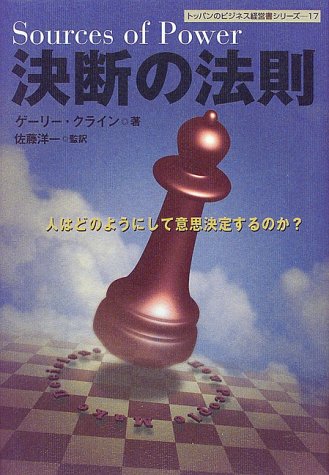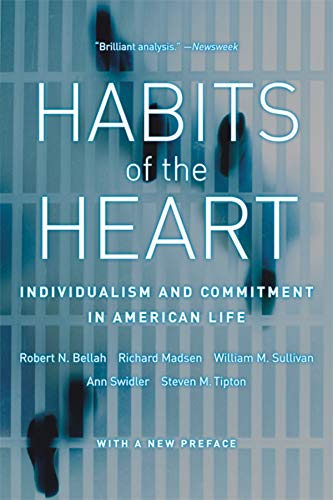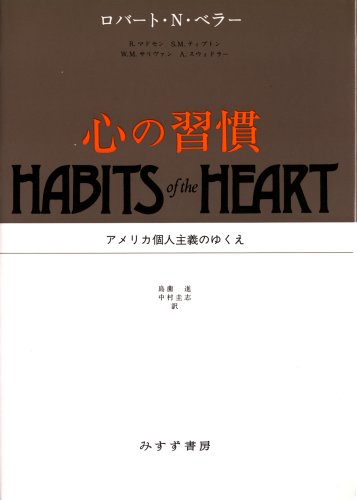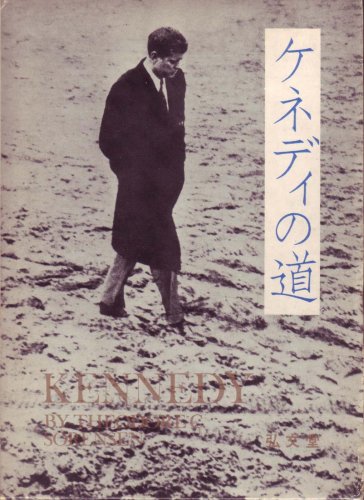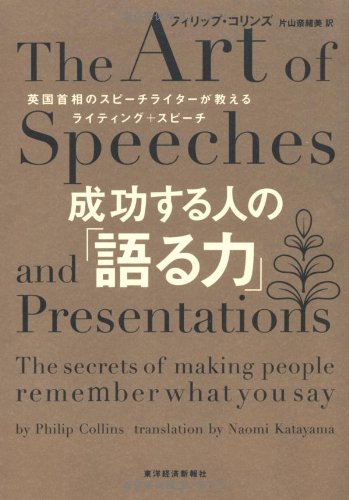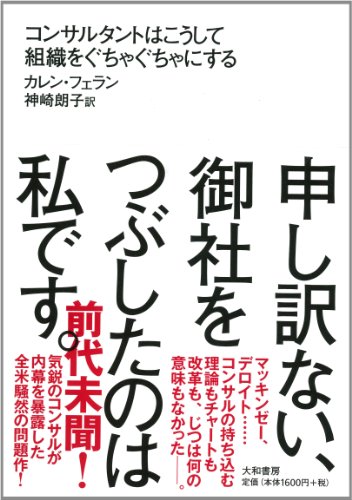まえがき
『消防活動の守則は、軍隊の〈一般守則〉にならって作成されるものと決定された。』
リスト
- 火災状況。火災の現況およびその状況予測について常に情報を得ておくこと。
- 指示。自分の出す指示を正確に理解し、いかなるときもそれに則って行動すること。
- 優先順位。自分の任務の要所を見きわめ、優先順の高い作業から取りかかること。
- 退避計画。常に退避を考慮にいれ、その計画に基づいて爆発的炎上の際は部下を誘導すること。
- 偵察。自分の責任下の火災地域をくまなく偵察すること。
- 通信。近くにいる分隊、部下、上官との定時連絡を確立・維持すること。
- 機敏さ。状況の変化をいち早く理解し、直ちに計画を修正・実行すること。
- 監視。あらゆる危険な事態に備えて、監視要員を配置すること。
- 規律。自分の指揮下にあるすべての隊員の統制を確立・維持し、いかなるときも隊員の所在および行動を把握しておくこと。
- 指揮。自分が消火の任にあたらせた隊員が適切な指揮のもと、確実に指示を理解できるようにすること。
あとがき
まえがきを含めてノーマン・マクリーン『マクリーンの渓谷―若きスモークジャンパー(森林降下消防士)たちの悲劇』からの引用です。Wikipedia(英語版)に”Ten Standard Firefighting Orders“がありますが、本書とはやや細部が違っています。
まえがきに示したように、軍隊の〈一般守則〉を雛形として作成されたとのこと。これを作成したときのエピソードとして、元海兵隊員だった森林保護官が『たまたま外のバス停に立っていた海兵隊員をつかまえて、二人で〈一般守則〉を素早く“復元”してみた』と書かれています。
十か条ものリストを諳んじるには、かなりの努力が必要です。どのように活用されているのか、さらに調べてみようと思います。
- タイトル: マクリーンの渓谷 若きスモークジャンパー(森林降下消防士)たちの悲劇
- 著者: ノーマン・マクリーン(著)、水上 峰雄(翻訳)
- 出版社: 集英社
- 出版日: 1997-07-25