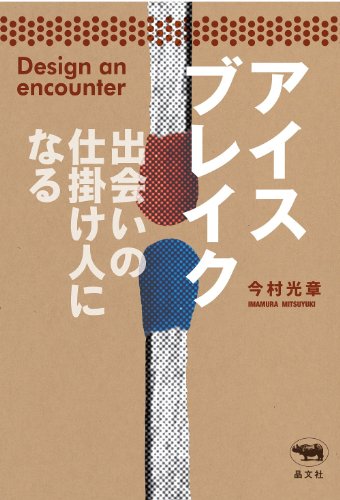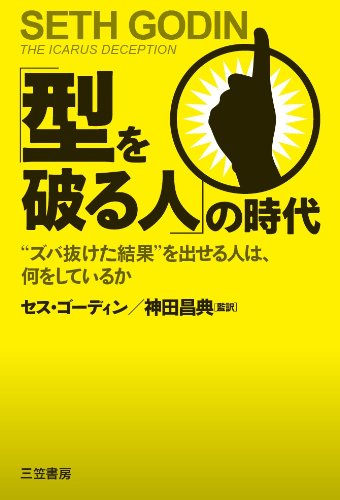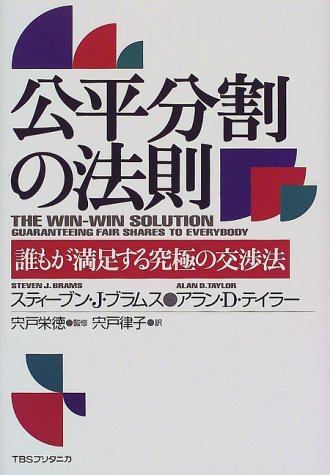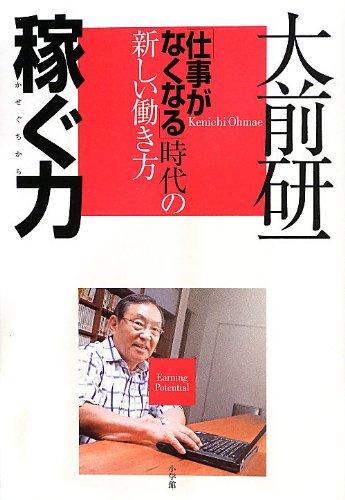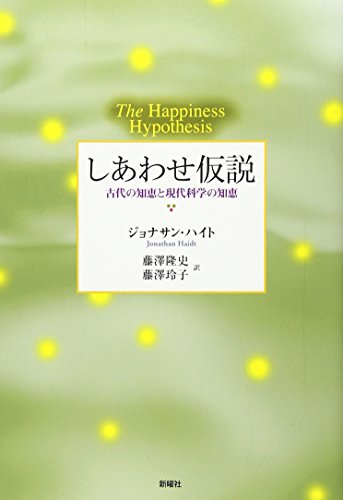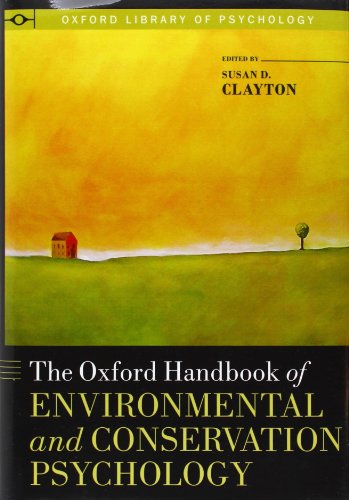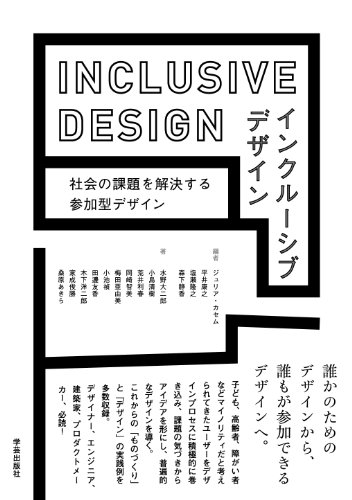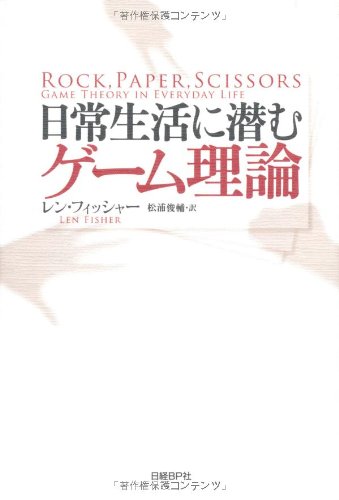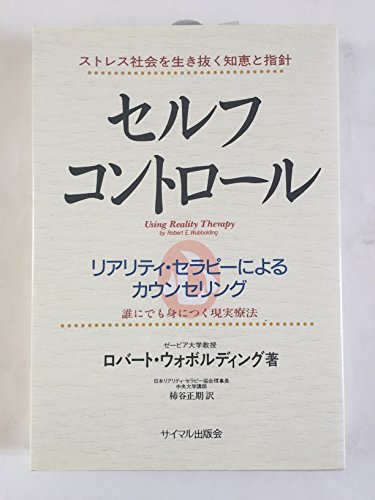まえがき
『アイスブレイカーとして、見知らぬ人たちの集団の前に立つ時、まずは三つのポイントがある。』
リスト
- 参加者にアイスブレイカー自身を知らせる
- 自分との共通点を見つけてもらう工夫をする
- アイスブレイカーが先に「いま、ここ」の生の気分を語る
あとがき
まえがきを含めて今村 光章『アイスブレイク』より。リストは目次より引用しました。本文中にも正式な?リストがあるのですが、微妙なところで目次のほうが出来がよいように感じたので。
先に知らせてから、知らせてもらう。第2項目と第3項目の順序が逆のほうがスッキリ覚えやすかったかも。
- タイトル: アイスブレイク
- 著者: 今村 光章(著)
- 出版社: 晶文社
- 出版日: 2014-06-13