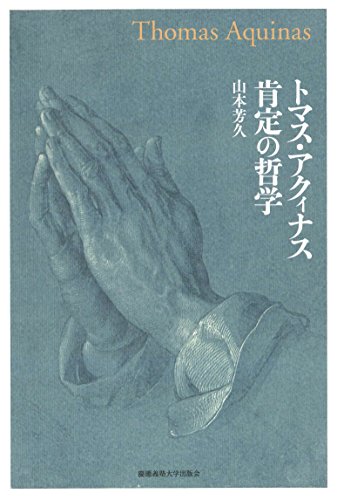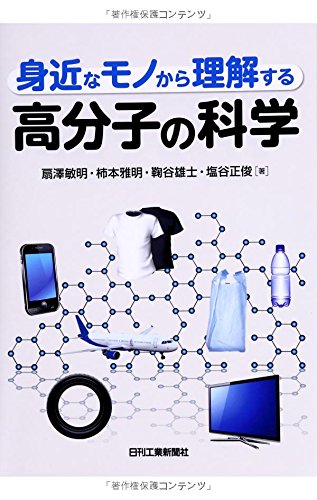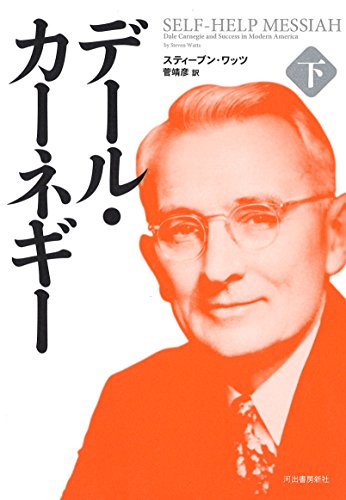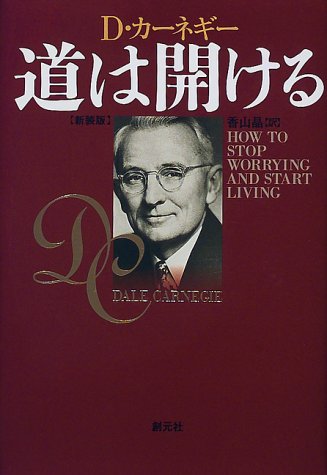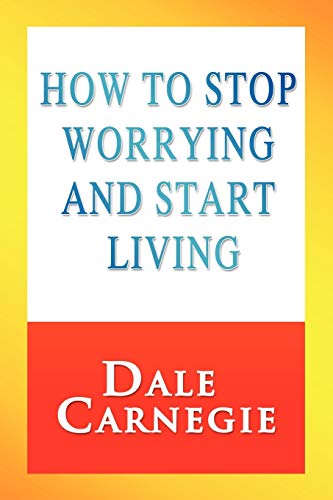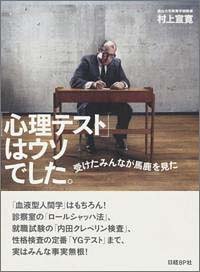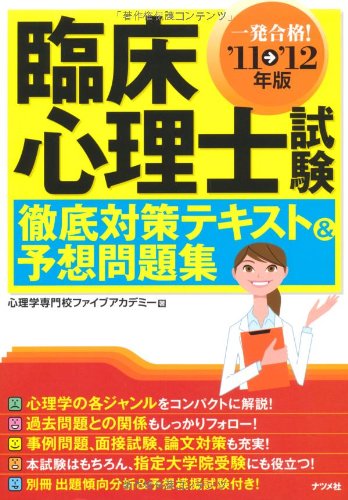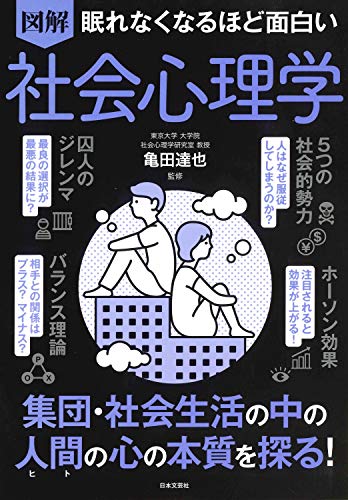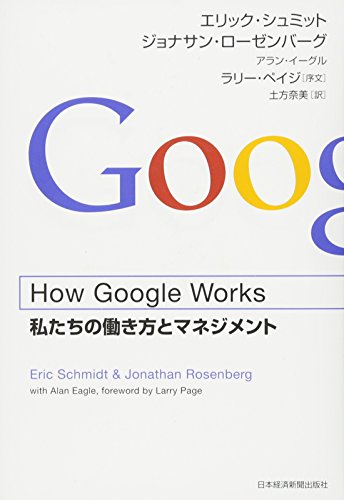まえがき
『トマスは諸々の感情を区別し連関させる独自の観点を提示している。』
リスト
- 【愛と憎しみ】愛は善との共鳴を意味し、憎しみは悪との不共鳴を意味している。何らかの善を愛しているからこそ、それを脅かす悪に対して憎しみが生じてくる。
- 【欲望と忌避】何らかの善によって愛が呼び覚まされると、その善を実際に獲得しようとする欲望が生じてくる。何らかの悪によって憎しみが呼び覚まされると、その対象を避けようとする忌避の念が生じてくる。
- 【喜びと悲しみ】何らかの善によって愛が呼び覚まされ、その愛に基づいて生じてくる欲望が無事に満たされると、喜びが生じてくる。何らかの悪によって憎しみが呼び覚まされ、その憎しみに基づいて生じてくる、その悪を避けようとする忌避の念にもかかわらず、その悪に逃れようもなく捉えられてしまうと、悲しみが生じてくる。
- 【希望と絶望】あるものが善であり、未来のものであり、獲得困難であり、かつ獲得可能であるとき、それは希望の対象となる。前三者の条件を満たすものが獲得不可能であるとき、それは絶望の対象となる。
- 【怖れと大胆】怖れは抵抗困難な未来の悪からの退避を意味しており、大胆は困難な未来の悪への接近を意味している。
- 【怒り】怖れと大胆は未来の悪に関わるのに対し、怒りは既に現在のものとなった困難な悪に関わる。怒りには、対立する感情がない。
あとがき
まえがきを含めて、山本 芳久『トマス・アクィナス 肯定の哲学』(慶應義塾大学出版会、2014)より。リスト項目は本文からの編集・引用です。
前3項目6種類の感情が「欲望的な感情」、後者が「気概的な感情」(困難が伴う場面で発現してくる感情)とのこと。感情を対称的・構造的に捉えようというアプローチは、プルチックを思い出します。
- タイトル: トマス・アクィナス 肯定の哲学
- 著者: 山本 芳久(著)
- 出版社: 慶應義塾大学出版会
- 出版日: 2014-09-17