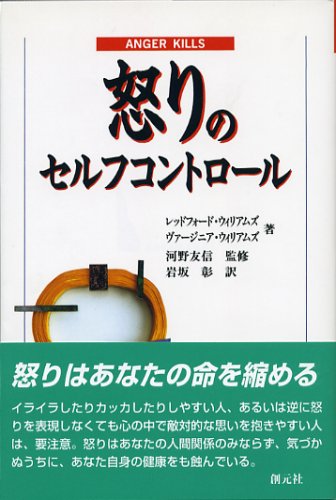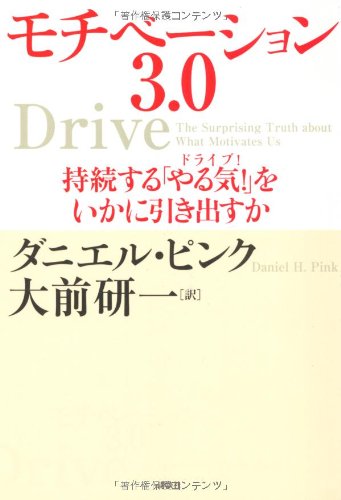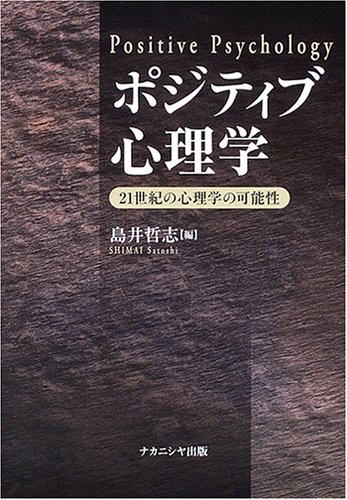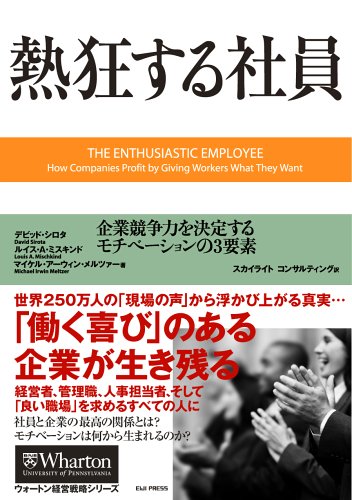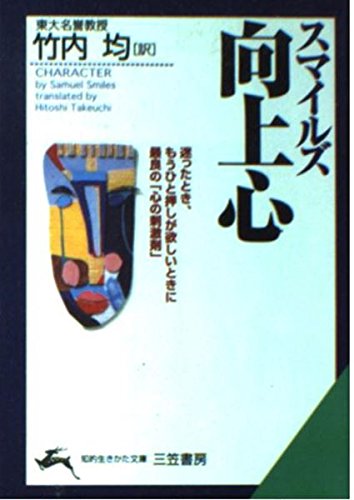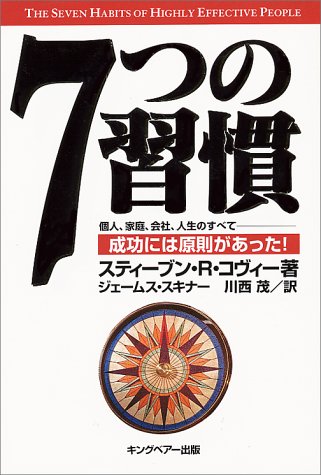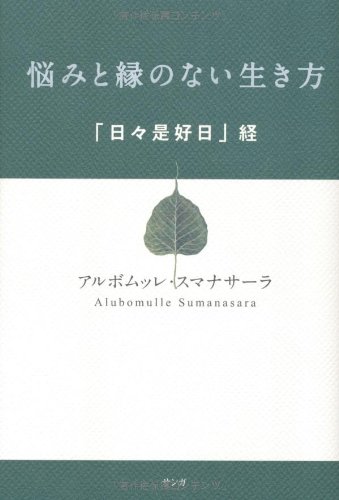まえがき
「怒りは人を殺す」。敵対性の高い人は健康を害しやすいという研究があるそうです。その「敵対性」はどんな側面から測れるのでしょうか。
リスト
- 【皮肉】一般に他人の意図を疑う態度のこと。このような態度をもっていると、つねに他人の「不品行」に対して身構えるようになります。
- 【怒り】皮肉な態度をもつ人間の、他人が間違った行動をとるのではないかという疑いから生じることの多い情動。
- 【攻撃性】敵対心をもちやすいやすい人間が、怒り、いらだちなどの不快な感情によって駆り立てられる行動。
あとがき
『怒りのセルフコントロール』より。この本には、この3側面の強さを測るテストがあります。自分ではまあ温厚な方なんじゃないかと思っていたりするわけですが、「行動」にこそ表さないものの、「態度」や「情動」面では、怒りの種みたいなものを抱えているなあ、なんて発見があったりしました。
- タイトル: 怒りのセルフコントロール
- 著者: ウィリアムズ,レッドフォード(著)、ウィリアムズ,ヴァージニア(著)、Williams,Redford(原著)、Williams,Virginia(原著)、彰, 岩坂(翻訳)
- 出版社: 創元社
- 出版日: 1995-05-01