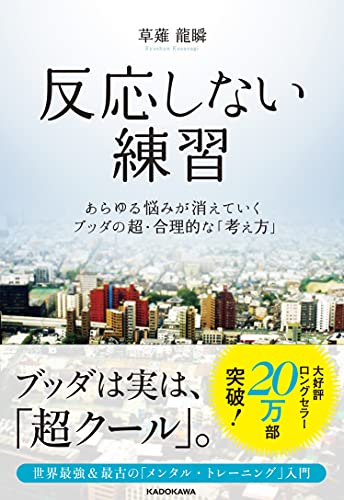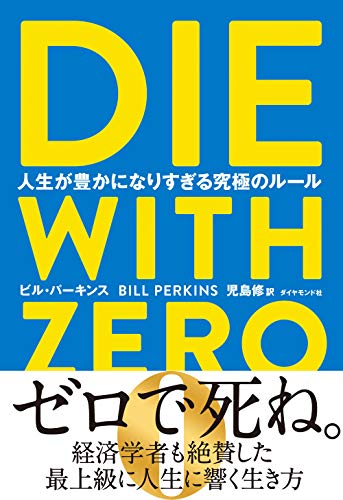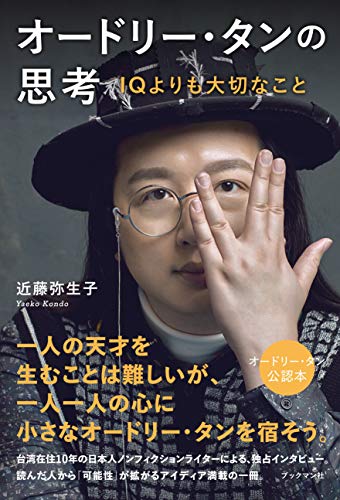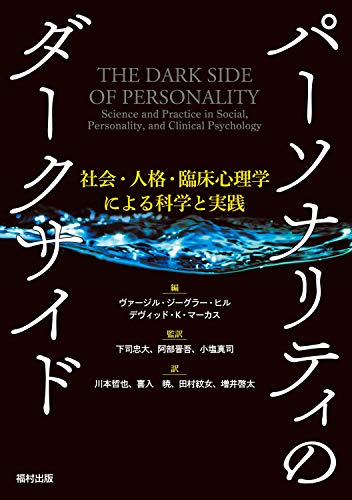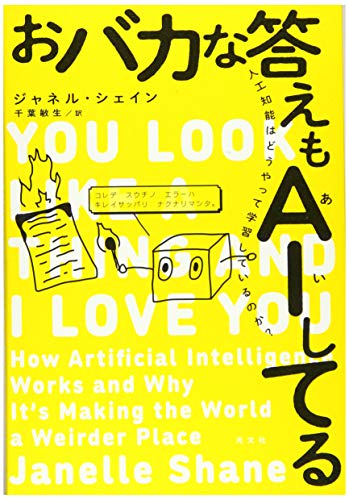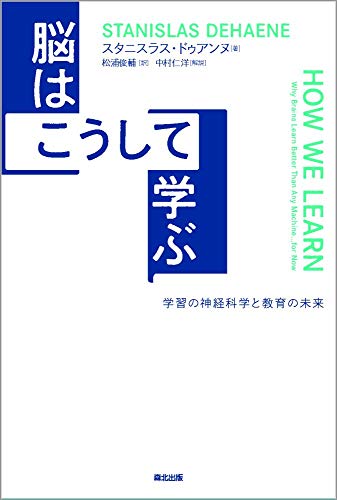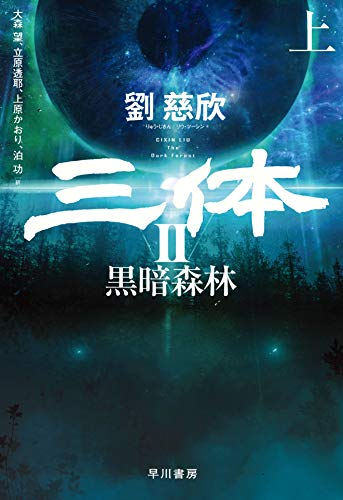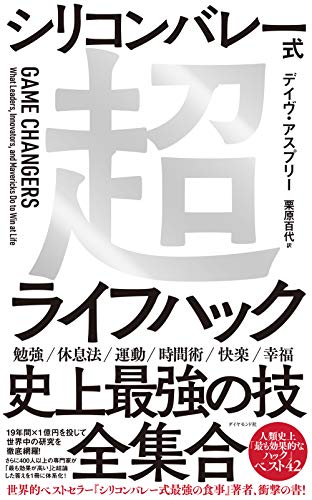まえがき
『道の者よ、迷いに満ちたおのれの心の状態に気づくがよい。そこには〝五つの妨げ〟がある。(略)気づくがよい。このような心の状態では、物事をよく理解することも、正しく考えることもできない。ゆえに苦しみの連鎖は、いつまでも続くであろうと。』
リスト
- 快楽に流される心(貪欲) ── 映像や音、匂い、味、触覚など「五官の快楽」に流れる心
- 怒り(瞋恚) ── 不快、不満、悲しみ、ストレス、他人への悪意など、心をざわつかせる感情
- やる気の出ない心(惛沈・睡眠) ── 眠たい、面倒くさい、ラクしたい、手を抜きたい、疲れて元気が出ない、といった状態
- そわそわと落ち着かない心(掉挙・悪作) ── 雑念や妄想だらけで、作業が手につかない状態
- 疑い(疑) ── 自分や他人、将来のことを悪く考えてしまう心
あとがき
まえがきを含めて、草薙龍瞬 『反応しない練習: あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」』(KADOKAWA/中経出版、2015年)より。
まえがきは、『若き修行者への訓誡 マッジマ・ニカーヤ』からの引用とあります。リストは本文からの編集・引用。ただし(貪欲)などの語は 五蓋 – Wikipedia からの引用です。タイトルの「五蓋」もこちらで付けました。
人生は〝正しい努力〟から〝五つの妨げ〟を引いた「残り」です。
はじめの2項目は三毒(貪瞋痴)の貪と瞋と重なっているようにみえますが、パーリ語を見ると違う言葉になっているので、カバーしている範囲が違う模様。
- タイトル: 反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」
- 著者: 草薙龍瞬(著)
- 出版社: KADOKAWA/中経出版
- 出版日: 2015-07-31