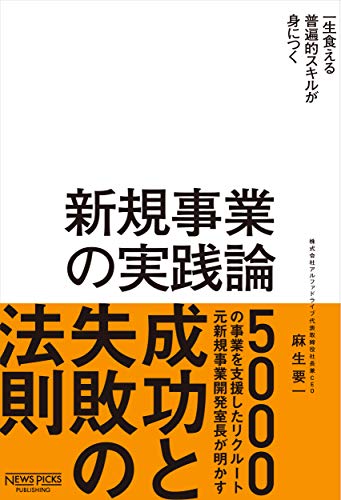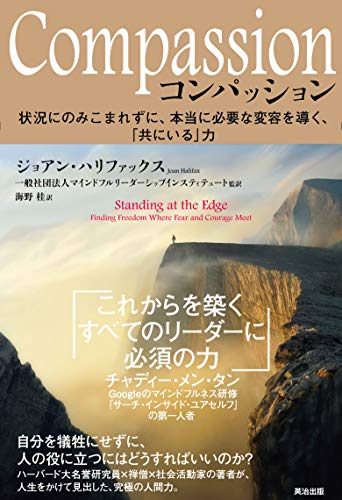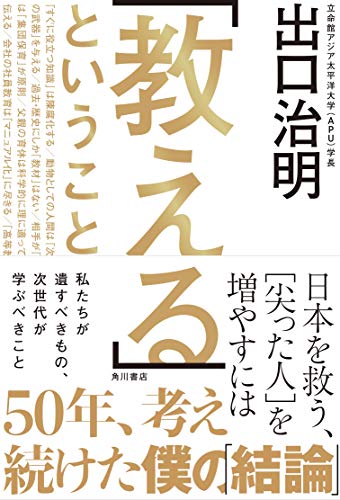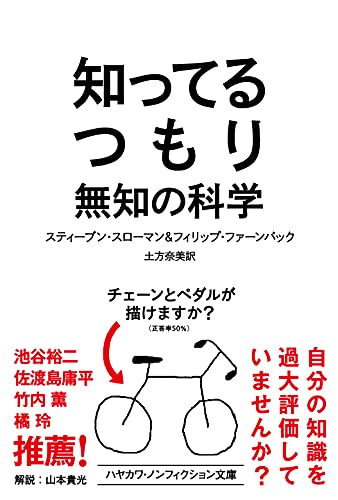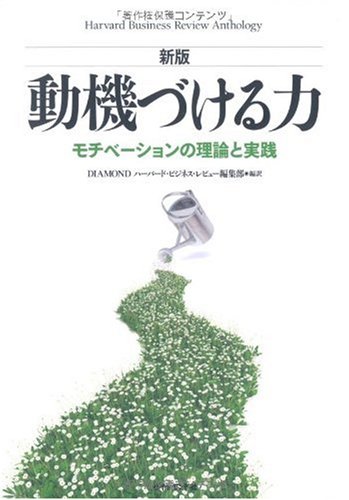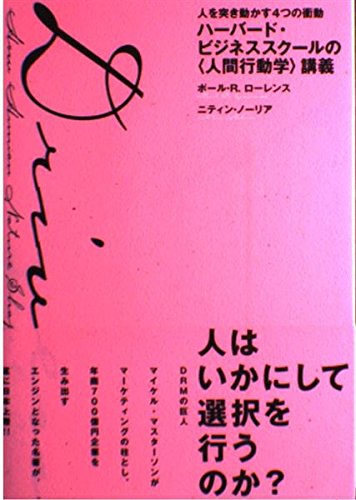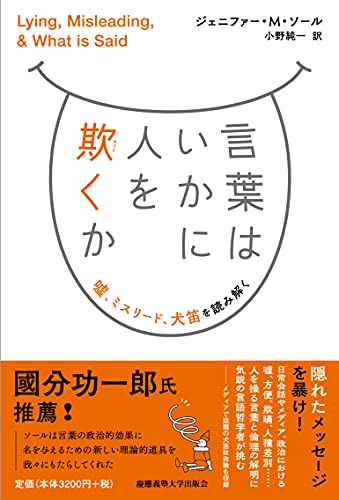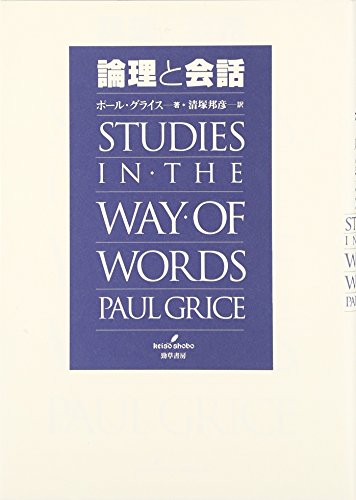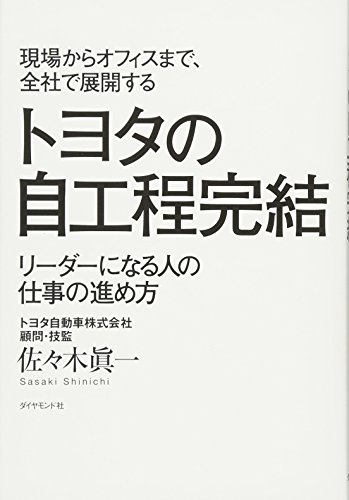まえがき
『社内会議で行われる「重箱の隅をつつく細かい質疑」(略)において重要なのは「明確に回答できること」、そして「そのための準備が万全であること」です。』
リスト
- 数値ロジック: 事業計画書の全項目について、その数字である理由を用意する
- 顧客の生の声: 見込み顧客の実際の言葉を用意する
- リスクシナリオと撤退ライン: 予想される状況変化と対処、これ以上遅れたら撤退、というシミュレーションをする
- 関連諸法規の提示: 事業が抵触する可能性のある法律や規制、社会的ルールがあるかを調べる
- 社内キーマン・社外権威者のコメント: 利害関係者となりそうな社内のキーマン、および社外の権威者からコメントをもらう
- 空気を読んだ戦略図: 新規事業が全社戦略に対して持つ意味合いを図示する
あとがき
まえがきを含めて、麻生要一『新規事業の実践論』 (NewsPicksパブリッシング、2019年)より。リストは本文を編集しつつ引用しました。
現在の日本の大企業のなかで新規事業を立ち上げるという文脈のなかで、具体的なコツがたくさん載っていました。
準備の視点は、決裁者が上司に説明できるか。ありそうでないというか、貴重なリストと思えたので収集。
- タイトル: 新規事業の実践論
- 著者: 麻生要一
- 出版社: NewsPicksパブリッシング
- 出版日: 2019-12-06