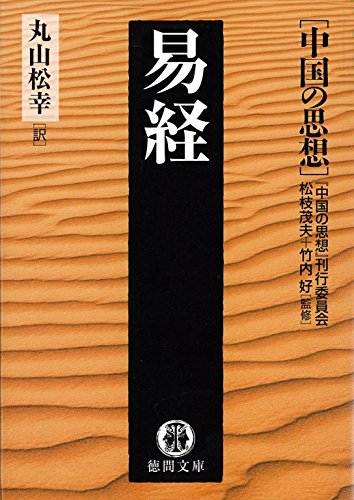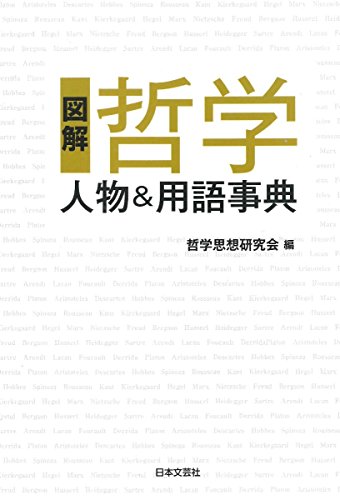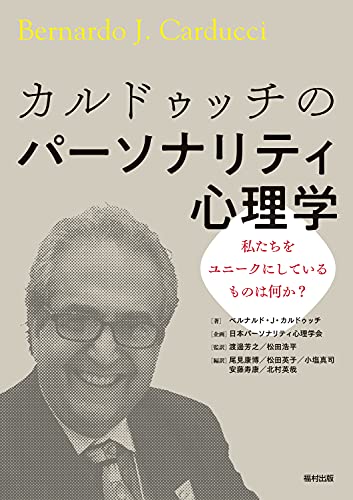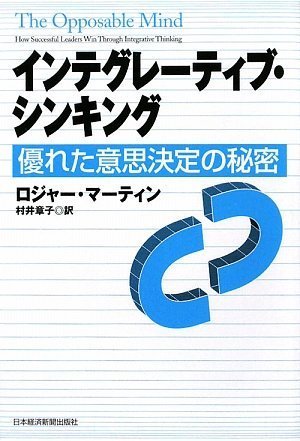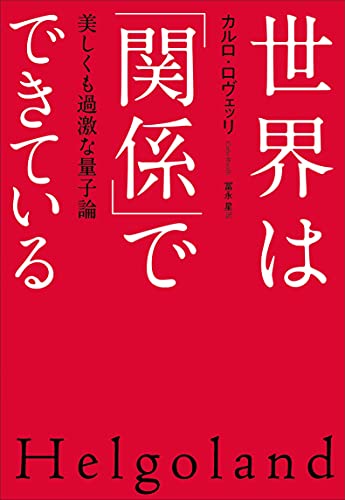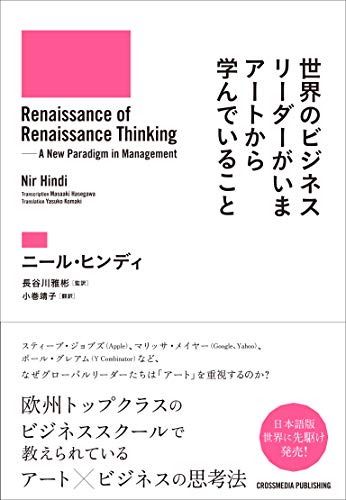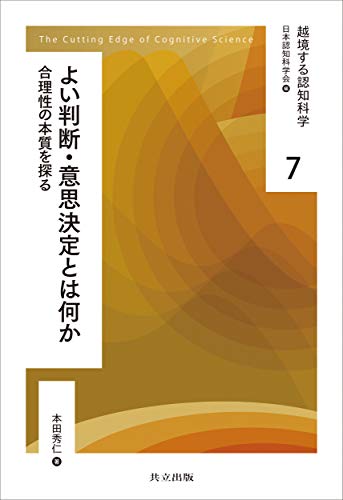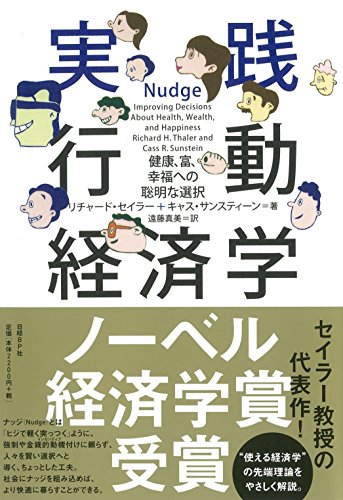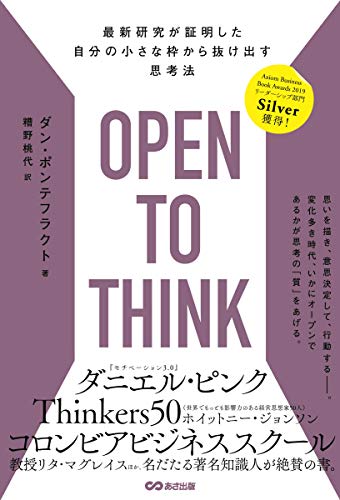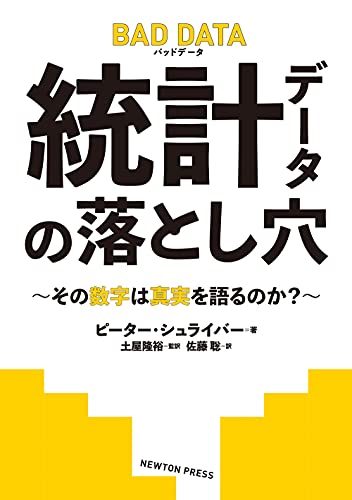まえがき
『1970年代以降、多くの非営利団体が仕事への取り組み方を変えようと、事業評価の手法を採用し始めた。その一般的な手法のなかにロジックモデルと呼ばれるものがある。(略)ロジックモデルはあらゆる事業を四つの要素に分解する。』
リスト
- インプット(もしくはリソース): 事業に投入されるもの。財務的な入力(金銭)から、ボランティアの時間、設備、土地やほかのハード的なリソースなど。
- アクティビティ: 事業の実施内容。印刷したパンフレットの部数、講演回数、意思が請求できる時間など。アクティビティはアウトプットにまとめられる場合もある。
- アウトプット: 実行されたアクティビティによって生成されるもの。授業に出席した人数、治療を受けた患者数など。
- アウトカム(およびインパクト): 意識、技能、知識、状況、状態、行動の変化であり、インパクトはこうしたものの長期的な変化である。
あとがき
まえがきを含めて、ピーター シュライバー『BAD DATA 統計データの落とし穴: その数字は真実を語るのか?』 (ニュートンプレス、2021年)より。
まえがきにある通り1970年代に開発されながら、「この手法はユナイテッド・ウェイ・オブ・アメリカが『Measuring Program Outcomes』(事業のアウトカムの測定)を出版する1990年代中ごろまで、ほとんど注目されなかった。」とのこと。
アウトプットとアウトカムを分離したところが要点ですね。後者をどう定義し、どう測るか。
「ロジックモデル」で検索すると最上位に来たのが『国際競技力向上施策の効果に関する評価について』(文部科学省、平成18年)という文書。この文書ではアウトカムをさらに3層に分けて定義していました。
ちなみに本書はタイトルから予想される内容に反して、数式も図もなくひたすら文章が続く本です。
ある目的の達成度合いを測るために指標を設けると、いつしかその指標を好ましい方向に操作することが目的と化し、当初の目的が損なわれる。そういったケーススタディをこれでもかと読ませてくれます。